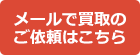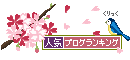世田谷区烏山にて買い入れ:哲学・思想書、人文書、専門書、クワイン、ヴィトゲンシュタイン、西田幾太郎
お客様からヴァージニア・ウルフの『燈台へ』を譲っていただきました。
ヴァージニア・ウルフは1882年にイギリスのロンドンで生まれました。ウルフの回想によると1895年まで一家は毎年夏をコーンウォール州のセント・アイヴスで過ごしており、ここで家族と過ごした思い出や風景などが『燈台へ』の下敷きとなったようです。(Wikipediaを読んで初めて知りました。)
ヴァージニア・ウルフを語るときに「意識の流れ」というキーワードが多用されます。「意識の流れ」とは日本の哲学者西田幾多郎や夏目漱石も影響を受けたアメリカの心理学者ウィリアム・ジェイムズが提唱した心理学の概念で、ジェイムズは『純粋経験の哲学』の本の中で【人間の意識は静的なものの集合や羅列ではなく、動的なイメージが流れているものである】と論じました。まさにウルフの小説の中では、語り手の人称が移動しながら、意識のバトンを繋ぐように話が展開していきます。
例えばわれわれの日常生活の中。わたしは家に向かって帰っている。しかしその帰り道はただの職場からの、学校からの平坦な帰り道ではなく、その日に起こったこと、もしくはかつてあったこと、もしかしたらこれからあるかもしれないことなどが、気候や風景、例えば通りがかったびっこをひく犬や、冬のアオサギの白い胸の髭が風に揺れる様など、その他さまざまなものやことに左右されて時間を飛び越える帰り道である。そこで想起されることは、誰にも言うことはなく、誰にも言うつもりもなく、そこで現れ、消えていく。しかしわたしはそこをまた別のある日に歩いた時に、かつてここで感じたことを覚えていたりする。ということは記憶とはわたしの中だけでなく、場所が持っているとも言えるかもしれない。(しかし「意識の流れ」を書いた、と言ったからといってヴァージニア・ウルフの本が説明できるわけは毛頭なく、そんなことはどうでもいいことでしょう。)
この本は第一章「窓」、第二章「時は逝く」、第三章「燈台」の全三章からなり、最初の「窓」ではラムジイ夫妻と8人の子どもたち、そして招かれた友人たちが夏のある一日を別荘で過ごしており、第二章でその名の通り時は10年流れ、第三章「燈台」では10年後のまたある一日が描かれます。
作中、ラムジイ婦人は膝の上の息子に絵本を読んで聞かせている時に、浜辺からの波のささめきに捉えられます。それは、近くで議論していた男たちの心地よいバリトンの声が急に止んだ後だっただけに、婦人を強く捉えました。われわれの事情や些末な出来事など無関係に非人間的に鳴り響く波のささめきを聴いて、婦人ははそこですべては流れていくことを、消えてゆくことに想いを馳せます。しかし作品全体にわたしが感じた印象はむしろ消えることなくそれはあり続ける、ということでした。それはちょうど、いびつな線が描かれた薄い遊び紙が何枚も重なっていくように、かつてあったこと、そして今は無いものたちが、直線的な時間ではなく、積み重なり、響き合うような印象でした。その空間自体が記憶しているような。
招かれた友人の一人である画家のリリー・ブリスコウは、島からの風景を作中描き続けます。一筆一筆の運動が彼女の外界と内面を混ぜ合わせながら、時には意気消沈し、絶望しながら、時には祝福し、肯定しながら風景を切り開いていきます。まさに、燈台へはこの力学で書かれたのではないでしょうか。リリーが画架に向かって、絵を描こうとする断片の描写たちはあらゆるなにかを創ろうとする人の背中を押すような素晴らしい文章です。
なにかあたらしいことを始めようかなとむずむずさせる春に、ウルフの『燈台へ』はいかがでしょうか?
タテ
お問合わせ・買取のご依頼
お問合わせ・ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。