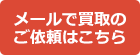明治時代の骨董屋の奉公とは?
カテゴリー/くまねこ堂通信
「骨董裏おもて」著:広田不狐斎/国書刊行会 という本を読みました。
著者の広田不狐斎さん(本名:廣田松繁、1897年~1973年)は、
日本屈指の古美術店「壺中居(こちゅうきょ)」の創業者で、
優れた収集家としても知られておられます。
9歳の時に父と死別し、おうちが困窮していたため、
12歳のときに1人故郷の富山を離れ、東京日本橋の骨董店に奉公することになります。
それ以来76歳で亡くなるまで、骨董ひと筋の道を歩まれました。
この本には、その六十有余年の歳月を綴る多彩なエッセイ150篇が収録されています。
全編を通じて、著者の骨董品に対する生涯にわたる誠実な愛情と、
徳の高い真摯なお人柄が伝わってきます。
この本はこれからも大切に持ち続けて、時折ページを開きたい、そう感じました。
さて、明治時代の骨董店での奉公は、いったいどんな様子だったのでしょうか。
こちらの文章から、その厳しい労働風景が伝わってきます。
——————————————
(抜粋)
主人が名古屋地方から関西方面に仕入れに行って帰京する時には、
荷車を曳いて新橋の駅(今の汐留駅)へ品物を積みに行きました。
また新潟、富山、金沢等の北陸方面に仕入れに出かけ、たくさんの品物を持ち帰るのを
その都度上野駅まで出迎えに行きましたが、朝の七時頃に列車が到着する時などは、
女中さんが起きてくれぬので、五時頃に起きて冷飯に漬物で朝食をすませて、
暗い中を車を曳いて上野駅に出かけたものです。
これがまた暑い時や温かい時はまだよいが、冬の寒中など、
信越線は始終二時間や三時間は雪のために延着し、時には五時間十時間も延着して、
夜になってから着いたこともあります。
今日と違って、当時は延着する時間を知らしてくれぬために、
いくら遅れても店に帰るわけにもゆかず、駅の横口に荷車を置いて、
車を盗まれまいと車の上に腰をかけて、寒くても駅の構内に入るわけにもゆかず、
チラチラと雪の降る寒い中に震えながら列車の到着するのを首を長くして待っている時など、
つくづく小僧奉公の辛さが身にしみました。
北国から着く列車は屋根の上に北国の雪を積んだまま上野に参ります。
その雪をながめると望郷のやるせない心が湧き、
この汽車に乗ればなつかしい故郷に帰れるのにと思い、幾度か逃げて帰ろうかと思いました。
しかし母は私が奉公に出ると同時に家をたたみ、埼玉県のある製糸工場に働きに行っていて
郷里にはおりません。その時もしも母が国にいて、奉公がそんなに辛ければ帰って来い、
と温かい手を差しのべたとしたら、美術商としての今日の私はないわけです。
恐らくそのまま郷里にいついたことでしょう。今思うと感慨無量なものがあります。
夜遅く車を曳いて全身冷え込んで帰った時、奥さんが、
「御苦労だったね、疲れたろう、さあ、さあ、早くあったまっておやすみ」
と、ねぎらってくれる言葉より、主人が「ウドンでも取ってやれ」と言ってくれて、
熱い一ぱいのウドンを吹きながら食べるのが、
小僧にとってはどれほど有難いか知れませんでした。
(抜粋)
———————————————————————–
子供にこんな労働をさせるなんて今の時代では考えられないわけですが、
当時は当たり前の風景だったのでしょうね。
わずか12歳の時に親元を離れ辛く厳しい奉公に耐え、
生涯に渡る誠実な努力とお人柄で後年立派に功を成された著者の姿には、
ただただ頭が下がり、身が引き締まる思いがいたします。
よろしければシェアお願いします
2014年9月に投稿した古本出張買取り│くまねこ堂・妻のブログの記事一覧